「噛む力」で脳を活性化!咀嚼がもたらす驚きの健康効果
「噛む力」で脳を活性化!咀嚼がもたらす驚きの健康効果
「噛む力」で脳を活性化!咀嚼がもたらす驚きの健康効果
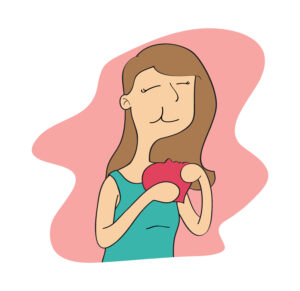
はじめに
「よく噛んで食べなさい」と子どもの頃に言われた経験は誰にでもあるでしょう。実は、この何気ない習慣が、単なる消化促進だけでなく、脳の活性化に大きく関わっていることが、近年の研究で次々と明らかになっています。
噛むという行為は、私たちが毎日何度も繰り返す動作ですが、その効果は想像以上に広範囲に及びます。記憶力の向上、認知症予防、ストレス解消、集中力アップなど、噛む力を鍛えることで得られるメリットは数多く存在します。この記事では、咀嚼と脳の関係について科学的な視点から解説し、日常生活で実践できる具体的な方法をご紹介します。
噛むことが脳に与える影響
脳への血流が増加する
噛む動作を行うと、顎の筋肉が動き、頭部全体の血流が促進されます。特に、咀嚼筋の収縮によって頸動脈から脳への血流量が増加することが研究で確認されています。脳は体重の約2%の重さしかありませんが、全身の酸素消費量の約20%を使用する非常に活発な器官です。
血流が増加することで、脳細胞に十分な酸素と栄養が供給され、脳の働きが活性化されます。特に、記憶を司る海馬や、思考や判断を担う前頭前野への血流が増えることが確認されており、これらの領域の機能向上につながるのです。
脳の神経細胞が刺激される
噛む刺激は、三叉神経を通じて直接脳に伝わります。この刺激が脳の広い範囲を活性化させることが、fMRI(機能的磁気共鳴画像法)などの研究で明らかになっています。ガムを噛んでいる時の脳活動を調べた研究では、前頭前野、側頭葉、海馬など、認知機能に関わる複数の領域が活性化することが示されています。
また、噛むことで脳由来神経栄養因子(BDNF)という物質の分泌が促進されることも報告されています。BDNFは神経細胞の成長や維持、シナプスの形成を促進する重要なタンパク質で、学習や記憶の形成に欠かせません。
認知症予防への効果
高齢者を対象にした疫学調査では、よく噛んで食べる人ほど認知症の発症リスクが低いことが報告されています。また、歯が少なく咀嚼機能が低下している人は、認知機能の低下が早く進む傾向にあることも明らかになっています。
動物実験でも、柔らかい餌だけで育てたマウスは、硬い餌で育てたマウスに比べて、海馬の神経細胞が減少し、記憶力テストの成績が悪くなることが確認されています。これらの研究結果から、噛むことが認知症予防に重要な役割を果たすことが科学的に裏付けられています。
噛む力がもたらす具体的な効果
記憶力と学習能力の向上
咀嚼が記憶力を高めることは、複数の研究で実証されています。学生を対象にした実験では、ガムを噛みながら学習した群は、噛まなかった群に比べて記憶テストの成績が有意に高かったという結果が得られています。
これは、噛むことで海馬への血流が増加し、新しい情報を記憶として定着させる能力が高まるためと考えられています。試験勉強や資格取得の学習時に、ガムを噛みながら行うのは、理にかなった方法といえるでしょう。
集中力と注意力の改善
噛むことは、集中力や注意力の維持にも効果があります。単調な作業を行う際にガムを噛むと、作業効率が上がり、ミスが減少することが報告されています。これは、咀嚼が脳の覚醒レベルを適度に保ち、注意力の低下を防ぐためと考えられます。
長時間の会議や運転中など、眠気と戦う必要がある場面で、ガムを噛むことが覚醒レベルの維持に役立つのは、多くの人が経験的に知っていることでしょう。
ストレス軽減とリラックス効果
噛むという行為には、ストレスを軽減する効果もあります。ストレスホルモンであるコルチゾールの分泌が抑制され、リラックス時に優位になる副交感神経の活動が高まることが研究で示されています。
また、一定のリズムで噛むことは、セロトニンという神経伝達物質の分泌を促進します。セロトニンは「幸せホルモン」とも呼ばれ、精神の安定や安心感をもたらす働きがあります。イライラした時や不安を感じた時に、ガムを噛むことでリラックスできるのは、このメカニズムによるものです。
反射神経と判断力の向上
咀嚼は運動能力にも影響を与えます。アスリートを対象にした研究では、ガムを噛みながら運動すると、反射神経や判断力が向上し、パフォーマンスが改善することが報告されています。
プロスポーツ選手の中には、試合中にガムを噛む習慣を持つ人が多くいますが、これは単なる癖ではなく、脳の活性化による集中力向上とストレス軽減を目的とした、理にかなった行動といえるでしょう。
噛む力を鍛える実践方法
一口30回を目標に
最も基本的で重要なのは、食事の際によく噛むことです。理想的な咀嚼回数は、一口につき30回とされています。現代人の平均咀嚼回数は10回から15回程度といわれており、意識的に噛む回数を増やす必要があります。
最初から30回を目指すのが難しい場合は、まず今より5回多く噛むことから始めてみましょう。徐々に回数を増やしていくことで、自然と30回噛む習慣が身につきます。
噛み応えのある食材を選ぶ
柔らかい食べ物ばかりでは、自然と咀嚼回数が減ってしまいます。意識的に噛み応えのある食材を取り入れることが大切です。根菜類(ごぼう、にんじん、れんこんなど)、きのこ類、海藻類、玄米、雑穀、ナッツ類、するめなどは、よく噛まないと飲み込めないため、自然と咀嚼回数が増えます。
野菜は大きめに切る、肉は塊のまま調理するなど、調理法を工夫することでも噛む回数を増やせます。
ガムを活用する
食事以外で噛む力を鍛えるには、ガムが手軽で効果的です。特に、硬めのガムを選ぶと顎の筋肉をしっかり使うことができます。ただし、長時間噛み続けると顎関節に負担がかかる可能性があるため、1回につき10分から15分程度にとどめましょう。
虫歯予防の観点から、キシリトール配合のシュガーレスガムを選ぶことをおすすめします。
左右均等に噛む
片側だけで噛む癖がある人は、顎の筋肉のバランスが悪くなり、顔の歪みや顎関節症の原因となることがあります。意識的に左右均等に噛むよう心がけましょう。
最初は難しいかもしれませんが、食べ物を口に入れる際に、普段あまり使わない側に置くようにすると、自然とそちら側で噛むようになります。
口周りの筋肉を鍛える
噛む力を支えるのは、顎の筋肉だけではありません。口周りの筋肉全体を鍛えることで、より効果的な咀嚼が可能になります。簡単なエクササイズとして、大きく口を開けて「あいうえお」と発音する、頬を膨らませたりへこませたりする、舌を口の中でぐるりと回すなどが効果的です。
これらのエクササイズは、いつでもどこでもできるため、テレビを見ながら、お風呂に入りながらなど、日常生活に取り入れやすいでしょう。
年代別の注意点とアドバイス
子どもの場合
成長期の子どもにとって、よく噛むことは顎の発達に欠かせません。柔らかい食べ物ばかり与えていると、顎が十分に発達せず、歯並びが悪くなったり、将来的に噛む力が弱くなったりする可能性があります。
子どもの頃からよく噛む習慣を身につけることで、脳の発達も促進されます。「よく噛んで食べようね」と声をかけるだけでなく、親自身が手本を見せることが大切です。
高齢者の場合
高齢になると、歯の喪失や入れ歯の不具合などで咀嚼機能が低下しがちです。しかし、認知症予防のためにも、できる限り自分の歯で噛むことが重要です。歯が悪い場合は、早めに歯科医院を受診し、適切な治療を受けましょう。
入れ歯の方も、定期的に調整してもらい、しっかり噛める状態を保つことが大切です。また、柔らかい食事ばかりでなく、食べやすく調理した噛み応えのある食材を取り入れることで、咀嚼機能の維持につながります。
まとめ
噛むことは、単に食べ物を細かくして消化を助けるだけでなく、脳の活性化、記憶力向上、認知症予防、ストレス軽減など、多岐にわたる健康効果をもたらします。一口30回を目標によく噛む習慣は、お金もかからず、今日から誰でも始められる最も手軽な健康法といえるでしょう。
食事の際に咀嚼回数を意識する、噛み応えのある食材を選ぶ、ガムを活用するなど、日常生活に取り入れやすい方法から始めてみてください。また、歯の健康を保つことも噛む力を維持するために不可欠です。定期的な歯科検診を受け、いつまでも自分の歯でしっかり噛める状態を保ちましょう。
よく噛むことで、脳も体も健康に。今日から「噛む力」を意識して、充実した毎日を送りましょう。
お子様にもおすすめ!怖くない、痛くない、安心して通える、優しいスタッフと楽しい雰囲気の歯科医院です。
いろどり歯科、是非、ご来院ください。

LINE
相談










