顎がガクガク鳴るのは噛み合わせのせい?
顎がガクガク鳴るのは噛み合わせのせい?
顎がガクガク鳴るのは噛み合わせのせい?
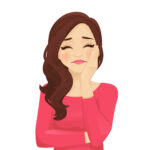
はじめに
口うるさい際に「ガクガク」「カクカク」みたいな顎関節症から聞こえる経験をした人は多いのではないでしょうか。 「は?」と考える方も多いですが、実際のところ顎関節の音と噛み合わせの関係は複雑で、単純に噛み合わせるだけが原因とは限りません。本記事では、顎がガクガク鳴る現象の仕組み、噛み合わせとの関係、そして正しい対処法について詳しく解説します。
顎関節の構造と機能
顎がクガク鳴る現象を理解するためには、まず顎関節の正常な構造と機能について知る必要があります。
正常な状態では、口を開閉する際に関節円板が下顎骨と一緒に前後に移動し、関節面同士の摩擦を軽減しています。 この関節円板の正常な動きであれば、口の開閉は無音で操作に行われます。
顎関節は他の関節と比較して特殊な構造を持っています。 膝関節や肘関節のような単純な蝶番関節ではなく、回転運動と滑走運動の両方を組み合わせた複合関節です。 口を開く際には、まずは関節頭が回転し、その後前方に滑走します。
顎関節音の種類と発生メカニズム
顎関節から発生する音は、その特徴によっていくつかの種類に分類されます。
クリックが発生するメカニズムは以下の通りです。 正常な関節円板は下顎骨と一緒に動くはずですが、かなりの原因で関節円板が前方にずれてしまうことがあります。 この状態で口を開いて、下顎骨の関節頭が関節円板を乗り越える瞬間にクリックして発生します。 これを「複位性顎関節円板転位」と呼びます。
一方、クレピタス音と呼ばれるギシギシ、ザラザラのような摩擦音もあります。 これは関節面の軟骨が摩耗し、骨同士が直接擦れ合うことで発生します。 クレピタス音は変形性顎関節症の症状として現れることが多く、クリック音よりも深刻な状態を示している場合があります。
また、一時的に発生する軽微なポップ音もあります。これは関節内の陰圧によって一時的に気泡が発生し、それが弾ける音で、かなり病的な状態を示すものではありません。
噛み合わせと顎関節音の関係
多くの人が疑問に思う「噛み合わせと顎関節音の関係」について詳しく見ていきましょう。 確かに噛み合わせは顎関節の健康に影響を与えますが、その関係は考えられているほど単純ではありません。
噛み合わせの異常が顎関節にマイナスの影響は、主に筋肉の緊張が出ます。 上下の歯の接触が必要な場合、咀嚼筋や首・肩の筋肉が常に緊張状態になります。
特に問題となるのは、初期接触や咬み合い干渉と呼ばれる状態です。 一部の歯だけが先に触れてしまう初期接触があると、顎は自然な位置を取らず、顎関節に不自然な力がかかります。 これにより関節円板の位置がずれ、クリック音の原因となることがあります。
しかし、重要なことは「噛み合わせの異常があっても顎関節痛が発生するわけではない」ということです。人間の身体は適応能力が高く、多少の噛み合わせの不正があっても、筋肉の協力により正常に機能することが多いです。
顎関節音の主な原因
顎関節音の発生には、噛み合わせ以外にも多くの関与が関与しています。
最も重要な課題の一つがブラキシズム(歯ぎしり・食いしばり)です。夜間の歯ぎしりや日中の食いしばりは、顎関節に過度の負荷がかかり、関節円板の変形や位置異常を保ちます。現代社会のストレス増加に伴い、ブラキシズムによる顎関節症が増加していると言われています。
外傷も重要な原因です。交通事故での鞭打ち損傷、スポーツ外傷、転倒による顎の打撲などは、顎関節の構造に直接的な損傷を与える、関節音の原因となります。特に成長期に受けた外傷は、その後の顎関節の発育に長期的な影響を考慮する可能性があります。
生活習慣も大きく関わっています。頬杖を作る、うつ伏せで寝る、電話を肩と耳で挟む、楽器演奏の時の大切な姿勢など、日常的に顎に負荷をかける習慣は顎関節症のリスクを高めます。
さらに、関節の構造的な特徴も影響します。 関節窩が浅い、関節円板が薄いなどの解剖学的特徴を持つ人は、顎関節症になりやすい傾向があります。 これらは遺伝的な要素も含まれるため、家族歴がある場合は特に注意が必要です。
ストレスと顎関節症の関係
現代社会において許容できないが、心理的ストレスと顎関節症の関係です。ストレスは直接的に筋緊張を保ち、間接的に行動パターンの変化を顎関節症に与えます。
ストレス状態がある人は、無意識のうちに歯を食いしばったり、頬の筋肉を緊張させたりする傾向があります。この状態が慢性化すると、咀嚼筋の持続的な緊張により顎への圧迫が増加し、関節円板の変形や位置異常を保ちます。
また、ストレスによる睡眠の質の低下も問題です。浅い眠りや中途覚醒が多くなる場合、夜間のブラキシズムが増加し、顎関節への負担が増大します。 さらに、ストレスホルモンの分泌増加は筋肉の回復を阻害し、炎症反応を促進するため、顎関節症の症状を悪化させる可能性があります。
職場環境や人間関係のストレス、長時間のデスクワークによる姿勢の悪化なども、複合的に顎関節症のリスクを高めます。特にコンピューター作業中の前かがみの姿勢は、頸椎の曲線を変化させ、顎関節の位置関係に影響を与えます。
診断と検査方法
顎関節音の原因を正確に診断するためには、専門的な検査が必要です。一般的な診断プロセスについて説明します。
まず、詳細な問診が行われます。症状の発症時期、音の特徴、痛みの有無、生活習慣、過去重要歴、外傷歴などを詳しく聴取します。 特に、発生するタイミング(口を開く時、閉じる時、咀嚼時など)は診断上の情報となります。
次に、視診・触診による理学検査が実施されます。口の開閉時の下顎の動き、口量の測定、咀嚼筋の触診、顎関節部の触診などを行います。音関節の聴力検査も重要な検査の一つで、聴診器を使って音の性質や発生タイミングを詳しく調べます。
画像検査では、まずはパノラマX線撮影により顎関節の骨構造を確認します。より詳細な診断が必要な場合は、MRI検査により関節円板の位置や形態、関節内の炎症の症状を評価します。CT検査は骨の変形や破壊の程度を詳しく調べるのに有効です。
最近では、咬合検査や顎運動解析装置を用いた機能検査も行われるようになりました。これらの検査により、噛み合わせの状態や顎の動きのパターンを客観的に評価することができます。
治療法とセルフケア
顎関節音の治療は、原因や症状の程度に応じて選択されます。多くの場合、保存的治療から開始され、段階的に治療法が選択されます。
初期治療としては、安静と生活習慣の改善が基本となります。 硬い食べ物を避け、広い口を開けることを控え、頬杖や歯ぎしりなどの悪習癖を改善します。 温湿布やマッサージによる筋肉の緊張緩和も効果的です。
薬物療法では、消炎鎮痛剤による炎症と痛みの軽減、筋弛緩剤による筋緊張の緩和が行われます。症状が強い場合は、関節内へのヒアルロン酸注射やステロイド注射が検討されることもあります。
スプリント療法は、顎関節症の治療の中核的な方法です。就寝時に装着するマウスピース様の装置により、歯ぎしりや食いしばりから顎関節を保護し、筋肉の緊張を緩和します。スプリントには様々な種類があり、症状に応じて選択されます。
理学療法では、顎関節の可動域訓練、咀嚼筋のマッサージ、姿勢矯正などが行われます。また、訓練や咀嚼訓練により、正常な顎機能の回復を図ります。
重度の症例では外科的治療が検討される場合もありますが、これは保存的治療で改善しない場合の最後の選択肢となります。関節鏡手術や関節円板の整復術などがありますが、適応は慎重に決定されます。
予防とライフスタイルの改善
顎関節音の予防には、日常生活での注意点を守ることが重要です。
食事に関しては、硬い食べ物や大きな食べ物を避け、軽く食べる習慣をつけます。ガムを長時間噛むことも避けるべきです。バランスの取れた食事と適度な咀嚼により、顎への負担を軽減できます。
姿勢の改善も重要な予防策です。 デスクワーク時には正しい姿勢の維持、睡眠時には適切な枕の使用、スマートフォンの長時間使用を控えるなど、首や顎に負担をかけない生活習慣を守ります。
ストレス管理も必須です。 規則正しい生活リズム、適度な運動、リラクゼーション法実践などにより、心身の緊張を考えることで、顎関節症の予防につながります。
定期的な歯科検診により、噛み合わせの状態をチェックし、必要に応じて調整を受けることも重要です。また、歯ぎしりや食いしばりの傾向がある場合は、早期にスプリント療法を開始することで、症状の進行を防ぐことができます。
まとめ
顎がクガク鳴る現象は、噛み合わせだけでなく、多様な関与が複合的に関与してます。ストレス、生活習慣、外傷歴、解剖学的特徴など、様々な要素が関節顎の健康に影響を与えています。症状が軽い場合は生活習慣の改善で改善することもありますが、持続する場合や痛みを伴う場合は、医師による適切な診断と治療を受けることが重要です。
最新の設備と優しいスタッフが揃った高槻市おすすめ、いろどり歯科では怖くない、安心の治療を提供致します!
是非、ご来院ください。

LINE
相談










